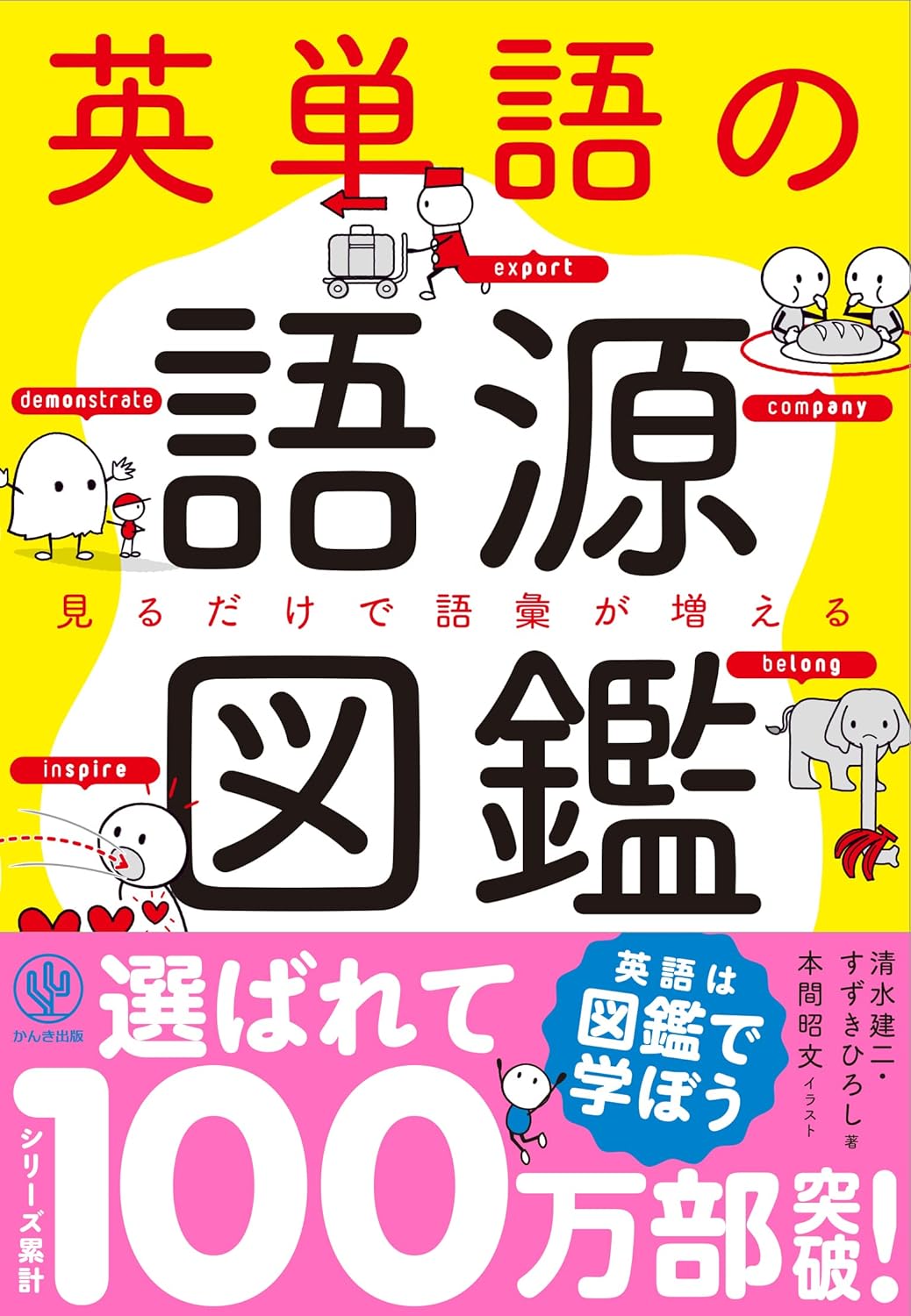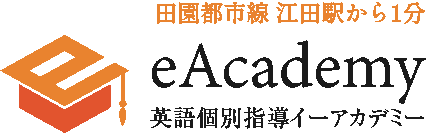eAcademyは横浜市青葉区、田園都市線江田駅そばにある英語の学び場です
前回・前々回と生徒に応じてどのように指導方法を変えているかをご紹介しました。
当校の生徒の多様性(その1)
https://learning-com.jp/blog/article.html?page=129
当校の生徒の多様性(その2)
https://learning-com.jp/blog/article.html?page=130
今回は、「英語の勉強が好きで、もっともっと英語力を伸ばしたい」と思っている生徒についてご紹介します。
当校には具体的に下記のような生徒がいます。個々の指導内容とともにご紹介します。
Nさん(中3):
小学校6年生の時から通っていて。英検準1級取得済み。小5で英検2級に合格したものの準1級が難しすぎて、とのことで通い始めました。将来は海外の学校で勉強したいと思っています。
Writingを見ていると文法の理解がまだ不充分なので、Murphyの「English Grammar in Use」で英文法の理解を体系的に進めています。
併せて、高校生対象のオンライン授業でReadingを勉強しています。
学校で帰国子女の子と同じクラスに入っているので、Listeningについてはそれで充分だと考えています。
Mさん(中1):
小5から始まった学校での英語の授業が楽しくて、もっと英語ができるようになりたいと通い始めました。今度英検2級に挑戦する予定ですが、まず問題なく合格するでしょう。急ぐ必要はありませんが、中学卒業までに準1級に合格することが当面の目標です。
これまでは単語を覚えて、英検の読解問題を解くことを中心に学習していましたが、基本的な英文法の理解は今後のためも必要なので、上記Nさんと同じくMurphyですが「Basic Grammar in Use」で基本的な文法理解に取り組んでいます。
それと同時に、Ladder Seriesを好きなもを選んで読むようにしています。Ladder Seriesはレベル1から5まで難易度が分かれているので、いろいろなレベルのものを読むようにアドバイスしています。
とにかくたくさんの英語に触れることが最も大切です。
Listeningについては、小学校時代に徹底的に発音を指導することから始めました。Ladder Seriesの音声を教材にして音読を行っています。
Iくん(高3):
当校で最も実力のある生徒です。準1級の1次は難なくパス、Speakingは何故か3点足りずに不合格、ふてくされて「英検はもういいや」、と言ってます。英語だけでなく他教科も成績優秀な、いわゆる秀才です。これから本格的に大学受験対策に入ります。
高校進学以来、彼にはとにかく多くの英文を読むことをアドバイスしています。
文法の勉強はほとんどやっていません。Readingの過程で文章構造が複雑なものに出会った際に、それを解析しながら文法項目を解説するようにしています。
単語を覚えることも、長文読解を通じてやるようにしており、彼自身もいわゆる単語帳で単語を覚えるということはやっていません。語源に基づいて単語を理解すること、接頭辞や接尾辞を押さえることで語感を養えており、本人もそれで充分にReadingはやっていけると理解しています。
当校の生徒のなかで最も多くの英文を読んでいます。
ListeningについてはOverlappingをやっています。ただ見ていて、音声のスピードについていこうとするあまり発音に落ち着きが無いように思われるので、Repeatingに変更することを考えています。
Native Speakerと同じ流暢さで話せる必要は日本人にはありませんので。
Aさん(高1):
上記Iくんの妹です。お兄ちゃんの勉強方法を良く聴いてマネするように言ってます。
高校に入って知らない単語がドバドバ出てくると戸惑っています。
お兄ちゃんから「Target1500」をもらったものの、面白くないので単語の覚え方を検討中です。「英単語の語源図鑑」をやることを考えています。
高校受験のために充分にやれなかったListeningの力を付けたいと本人も考えており、学校でもDictationをやっているとのことなので、その教材を使ってRepaeatingをやるようにしています。なかなか難しくて、思うようにできないようですが時間とともにできるようになるでしょう。
高校受験対策が本格化する前に、発音の指導をやっていたので、素地はできているので
他にもご紹介したい生徒がいるのですが、このくらいにしておきます。
上記に加えて生徒たちに伝えていることのポイントは以下の2つです。
1.量をこなす
とにかく
たくさんの英語に触れること。
英語は質より量であることを知ること。
言い方を変えると、量を伴わない質の向上はないとしること。
2.いろんな勉強をする
その人の英語力を決定するのは、最終的にその人の知識と教養なので、英語ばっかり勉強せずに他教科もしっかり勉強すること。
そしてたくさん本を読むこと。
せっかく縁あって当校に通ってくれるようになったのだから、
英語しかできない残念な人にならないでもらいたいと願っています。
eAcademy
横浜市青葉区
田園都市線江田駅そばの英語の学び場