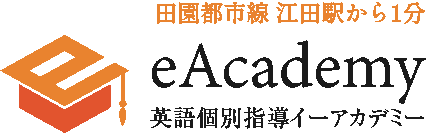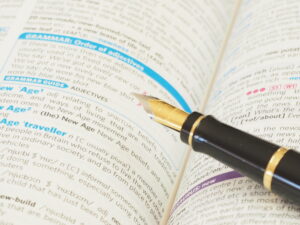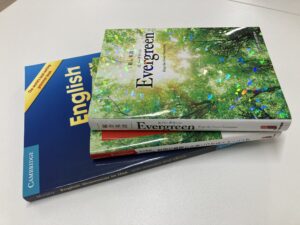2022 年 1 月 1 日公開
明けましておめでとうございます
2022年、明けましておめでとうございます。
2021 年 12 月 12 日公開
自律して勉強するために辞める生徒
開校してわずか1年ですが、それでも様々な経験をさせてもらい、いろいろと考えさせられることも多くあるものです。
2021 年 12 月 1 日公開
開校1周年に思うこと
昨年12月に英語専門塾として開校以来、イーアカデミーは無事に1周年を迎えることができました。
2021 年 11 月 30 日公開
英検はWritingで点を稼ぐ
まずは、下の数字をご覧ください。2級受験者:11名中 10名 Writingが最高得点だった受験者の数 です。英検のWritingは難しくありません。 2級受験者で3名が、650点満点中、632、638、625と95%以上のスコアを獲得、また3級受験者にも550点満点中、537と98%のスコアを挙げています。 英検のWritingは幾つかのポイントを押さえて、それを確実に実践すれば高得点をとることは簡単 です。
2021 年 10 月 7 日公開
受験終了後も通い続けてくれる生徒
某大学付属高校の内部進学テストが終わりました。このテストの結果によって進める学部が決まります。浪人の心配はないとはいえ、大学付属高校といっても厳しい環境にあるんだな、と思います。PS: この生徒は無事に志望学部に合格しました!
2021 年 8 月 20 日公開
何か一つの事に打ち込むことは、人生の選択を拡げることになる
2名の中3生が早々と推薦を得て高校進学を決めました。
2021 年 5 月 13 日公開
最初のうちは英語を書き取ることも大切
全員ではありませんが、当校では教科書の英文をノートに書き写してから日本語訳を考えることをしています。全ての英文を書いていると時間がかかるため、強制はしていません。私自身も書き写すことは必ずしも必要ではないと考えています。are ~」であるところを、「Tina and Ken has ~」と書いていました。
2021 年 4 月 13 日公開
質より量
量を伴わない質の向上はありません。英語の勉強も同じです。
2021 年 4 月 8 日公開
浪人生の受け入れ
当校は大学受験対策もサポートしています。
2021 年 2 月 27 日公開
学年末テスト対策
学校によってスケジュールは様々ですが、2月後半から3月前半は学年末テストの真っ最中です。開校間もない当校では、まだ受験生はいません。ですので学年末テストの準備に集中しています。