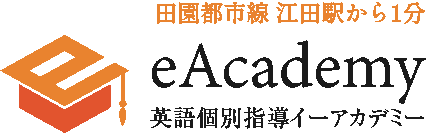2022 年 10 月 6 日公開
ポスティングもまた楽し
イーアカデミーは横浜市青葉区の英語専門塾です。eAcademy
2022 年 7 月 12 日公開
Writingはシンプルな文章で明確なメッセージを
某中学3年生の英語問題集にある英作文の問題です。It is important to learn English. You should(must / have to, etc.) learn English.(This is important.) Learn English.(This is important.)
2022 年 6 月 14 日公開
卒業生が遊びに来てくれました
当校に通っていた、現在は大学生の元生徒さんが連絡をくれ、遊びに来てくれました。
2022 年 6 月 1 日公開
生徒の多様性
イーアカデミーは英語指導に特化した塾です。 様々なバックグラウンドを持つ生徒が集まってくれることに、深く感謝するとともに、これら多様な生徒の多様な要望を汲み取り、適切な指導をこれからも行っていく所存です。 生徒在籍校一覧 高校: 中学: 小学校:
2022 年 5 月 18 日公開
単語を覚えるときは声に出して発音と一緒に
単語を覚えるときは、必ず発音しながら覚えましょう!
2022 年 4 月 21 日公開
ListeningとGrammarの関係について
ListeningにおいてもGrammarは重要です。 might drop below zero today.my drop below zero today.「L」と「R」の発音 | 英語個別指導 イーアカデミー – eAcademy – (learning-com.jp) 聴き取りとしては間違っていない 、ということです。しかし、これでは不正解です。何故か? my drop below zero today.語学学習ではGrammar、Reading、Listening、Speakingは独立した別々のものではなく、これらは有機的につながっているのです。
2022 年 2 月 18 日公開
「日本人」を英語で何という?
「日本人は~だ」といった文章を書く場面は、英語を勉強していると必ず出てきます。その時に「日本人」を英語ではどう表せば良いのでしょう?In regard to your question. This one is difficult and I had to think about it. 「Japanese」は単数でも複数でも使えるけど、「The Japanese」複数形で使うよね。 Mitsuo is Japanese. (singular) みつおは日本人だ I like the Japanese. (plural) 私は日本人が好きだ The Japanese people have many ancient traditions. (plural) 日本人にはたくさんの伝統的なものがある “Japanese people have many ancient traditions.” 「Japanese people」を使っても良いけど、ちょっと違う感じがするかな Therefore my thinking is that “the Japanese” is used for plural situations where as “Japanese” (without the The) is used for singular. The terms are somewhat interchangeable. 「the Japanese」は複数で使われて、「Japanese」は単数という感じだけど、どちらでも良い感じもするかな。 The Japanese culture is different from the west. 「The」が着いたほうがフォーマルな感じがする “I like Japanese.” It means I like the Japanese language 「I like Japanese」というと「日本語が好き」という意味 When you use “The Japanese …” it could refer to the third person. 「The Japanese」という時は、第三者の発言 For example I, someone who is not Japanese would say: 日本人は野球が好きだ。(日本人以外の人が発言する場合) Compared to if your are were Japanese you would say 上記の文章は(私達)日本人は野球が好きだ、という意味になる Same as if you were English you would say
2022 年 2 月 1 日公開
“skillful”という語の意味と語彙力をつける方法
ある中1生からの質問と、その質問を受けてからの生徒とのやり取りです。skill = (名):(~における)技能、能力、熟達:(すぐれた)技量、手腕 skillful = (形):上手な、うでのいい、技量のある、熟練した powerful(power), joyful(joy), awful(awe), careful(care), colorful(color) etc.
2022 年 1 月 20 日公開
“It is time we leave.” は何故間違い?
ある生徒から質問されました。